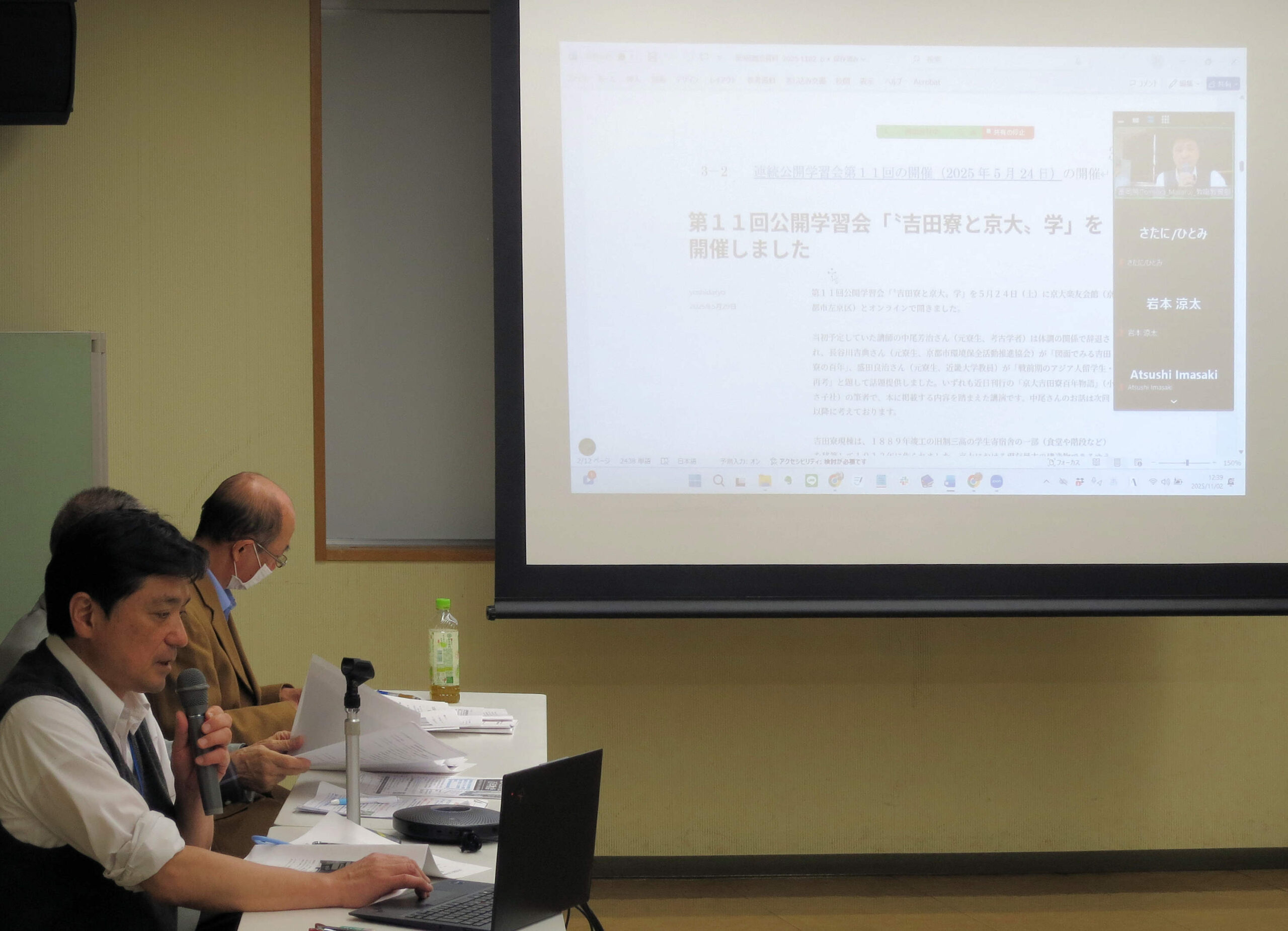「21世紀に吉田寮を活かす元寮生の会」の総会と、連続公開学習会「吉田寮と京大」学の第12回が、11月2日(日)に「こどもみらい館」(京都市)で開かれました。残念ながら総会成立に必要な数に達せずに集会となりましたが、有意義な意見交換と学習になりました。
最初に奈倉代表があいさつをしました。京大と吉田寮生との裁判が和解として決着し、現棟(木造棟)の耐震工事が具体化する状況を受け、「元寮生の会はますます必要となり、役割は大きい。忌憚のない意見交換を」と呼びかけました。
事務局より、この一年の活動について報告がありました。学習会や「京大吉田寮百年物語」の編集協力と出版、和解を受けた理事会声明と会としての申し入れ提出をしてきました。「和解によって、京大は吉田寮自治会との話し合い再開となるはずだが、そうなっていない。市民の声を京大に届ける必要がある。どのように京大に訴えるか議論したい」とまとめました。
続いて吉田寮生から大阪高裁での和解に至る経緯について報告を受けました。和解内容のポイントとして①吉田寮食堂の継続使用②現棟の補修(立て替えを含む)③補修後の被告寮生の入寮権限の維持と、原告(京大)の他の請求事項の放棄ーを挙げ、弁護団の受け止めとして「勝利和解」との評価を示しました。今後の活動について、寮内で話し合いを重ねて方向性について認識を共有し、全体で意見を一致できるよう取り組んでいるとのことです。
和解後の吉田寮自治会の取り組みとして、京大当局への対話再開の呼びかけとともに、署名活動の開始と、教員への働きかけを進めています。この間、教職員対象の吉田寮見学ツアーを行い、京大カレー部に所属する寮生がカレーをふるまうなどして、好評だったとのことです。11月祭への出展や、12月に集会を予定していることも報告されました。署名「吉田寮の自治と歴史的建築を未来へ!和解した今こそ対話の再開を!」は吉田寮自治会のホームページで呼びかけられおり、元寮生の会にも協力を求めました。
元寮生の会に対しては▽現棟を残すための取り組みと具体的な提案▽署名活動の周知▽自治会の活動支援ーが要請されました。
和解を受けて来年3月末までに現棟から引っ越しをしなければいけません。来年の入寮募集や現棟の機能の移行、現棟にある資料の取り扱いについて寮生に質問がありました。資料については、学外での保管場所の確保と費用支援も含め、会としてできることがあるかを理事会で考え、会員の皆さんに相談したいと思います。東大駒場寮のように会独自の拠点を構えて資料を引き受け、情報発信の拠点にすることも選択肢となりますが、費用面をはじめ検討が必要です。
不透明な状況である耐震工事については、「専門家を味方に」として計画策定にあたって近代建築、木造建築、建築文化財の専門家が入ることを求めることや、「(南寮など)一棟ずつ補修することで居住の継続と耐震工事を併せて進めることができる」との意見も出されました。
元寮生の会としての今後の活動について意見交換をしました。奈倉代表は「活気のある会でありたいが力不足でそうはなっていない。会員の皆さんがもっともっと21世紀に合った形で進めていただきたい」と話されました。理事会としては、半年をめどに代表の仕事を次期会長候補が引き継ぎ、来年の総会で顧問創設を含めた新体制について承認を得ることを方向性として示しました。
検討中となっている「百年物語」の出版記念を兼ねた企画を吉田寮現棟の保全をアピールする機会とすることや、立て替えではなく建物を残す工事を求めることが提案され、理事会とメーリングリストで意見を交わし、会員の皆さんに改めて提案することとしました。
続いて元理事の中尾芳治さん(考古学者、元帝塚山学院大教授)を講師に学習会「吉田寮(京大寄宿舎)を建築文化財として保存・活用する」を行いました。
自身が吉田寮に住んだ1956年から59年まで3年間の生活(当時は入学年は宇治寮)について、「寄宿舎記念祭」「三寮対抗運動会」、寮生による近隣の子どもたちへの「サマースクール」などの写真を交えて紹介されました。「経済的に恵まれなかった私が大学を無事卒業できたのは、奨学金と授業料免除、4年間を寮で過ごせたおかげであると、今も感謝の気持ちを忘れたことはない」「経済的恩恵だけでなく、吉田寮で過ごした3年間は、さまざまな学部の先輩・後輩と『一つの釜の飯を食って』生活を共にする中で、さまざまな専門分野や価値感に触れることができたことは私の人格形成に大きなプラスであったと感謝している」と話されました。
自身は「お世話になるので大切に使う。後輩のために入ったときと同じ状況に戻す」との考えで寮に暮らしていたが、近年に寄宿舎の仲間と訪ねた吉田寮現棟で廊下に生活用品があふれて雑然としていた状況を見て残念に感じたことを話し、木造棟での暮らし方の再考も求めました。
続いて京大や京都府教委、山根芳洋さんによる吉田寮の調査と、日本建築学会近畿支部や建築史学会が保存活用を求めて京大に提出した要望書を説明。「建築文化財として重要性が調査から明らかになっているが、大学が反応していない。重要性を認めて修復・活用するという姿勢がない。冷淡だ。吉田寮を残していこういう姿勢がまったくないと思わざるをえない」との懸念を示しました。
補修について、「市民と考える吉田寮再生100年プレゼン&シンポジウム」(2018年9月)で最も多くの支持を集めた、自身による再生・活用案「建築文化財吉田寮の保全と学生寮への再生」を紹介しました。北寮と南寮は現状維持したまま耐震補修し、火災に遭った中寮の一部は資料館や共有スペース、炊事場などに改修、建築文化財としての認識を持って寮生が生活するとの提案です。
京大楽友会館などが登録文化財に指定されている現況を踏まえ、吉田寮現棟と食堂も「登録文化財に指定登録して保存活用を図るべき」と強調、「動態保存して今後も学生寮として活用する」「大学・自治会の当事者だけでなく第三者を交えた『吉田寮保存・修復・活用委員会』を組織して検討する」「今後の吉田寮の保全・活用運動は、学内運動にとどめず広く市民と連帯する市民運動として拡大させていくべき」と提案しました。
「市民運動」について、自身が長年にわたって調査に携わり、保存運動にも協力してきた難波宮跡と環境整備について紹介。吉田寮についても「京都市民にも関わる問題として広げていく」ことを訴えました。工事計画の検討に第三者を加えることが「最大の課題ではないか」とし、元寮生の会としてどのように取り組むか考えてほしいとしました。吉田寮の保全について「危機感を持つ必要がある」「我々が運動を推進して勝ち取っていくしかない」「これからが正念場」と話し、参加者からは京都市が抱えるマンションなどの問題と合わせた運動を考えてほしいなどの提案がありました。